Program大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード
(Sustainability Award for Students by Students:#SASS2022)
現役の大学生が主体となり、高校生・中学生を対象にしたSDGs動画アワードを企画・運営。また、中学校および高等学校の総合的な学習(探究)の時間を活用し、SDGsを切り口とした大学生伴走型のPBL(課題解決型学習)プログラムを提供している。
SDGsをテーマに社会課題・地域課題の基礎をインプットした上で、高校生数人、大学生メンター1人でチームを組成し、自身等が興味のある地域課題・社会課題に対し、どのような解決策があるか、自分たちに何ができるかを、比較的年齢の近い大学生メンターと相談しながら検討、実行、発表まで行う。
検討結果や実施結果については、動画形式で生徒自身がまとめることで、学習の振り返りになるとともに、#SASS(大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード)に応募し、同様の取り組みを行う全国の同世代と切磋琢磨することが可能となる。
PBLプログラムの提供という入り口から動画コンテストによる成果発表、受験という出口まで一貫して生徒・学校と伴走することにより、現場の先生方の理解も得つつキャリア教育の推進を図っていく。
◆大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード 特設HP
https://www.sdgs-award.com/

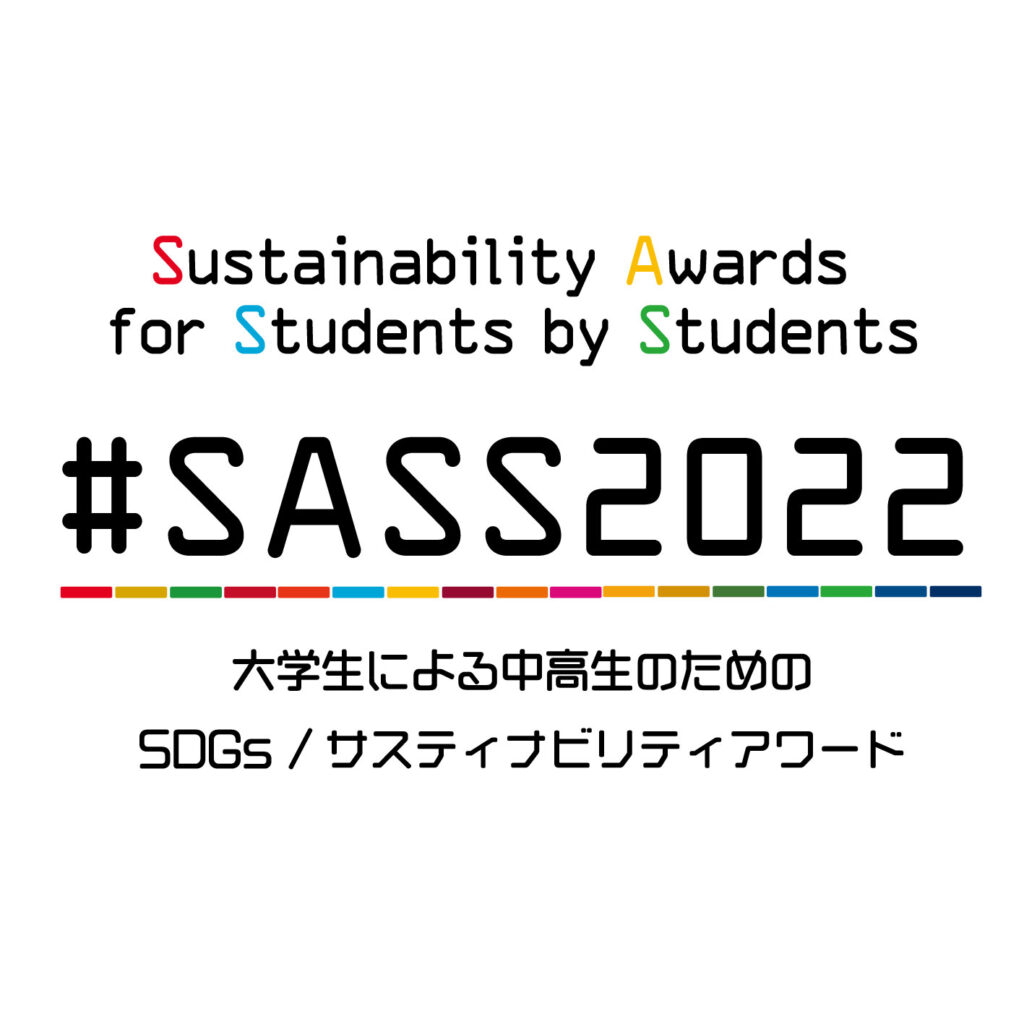

活動レポートReport
SDGsをテーマとした動画コンテストを通じて、探究活動の成果を実りあるものに
「じぶんごと、みんなごと、世の中ごとを増やして、『自分らしく生きる』をサポートしたい」をビジョンに掲げるアンカーでは、現役の大学生やOB・OGが主体となって、中学校および高等学校を対象としたSDGs教育、キャリア教育を幅広く展開している。
具体的な活動内容としては、総合的な学習(探究)の時間を活用して大学生伴走型のPBL(課題解決型学習)プログラムを提供するとともに、SDGsやキャリア形成をテーマとした教材の開発・提供なども行っている。加えて、こうした探究学習の成果を、広く全国の同世代と共有し、切磋琢磨することを目的に、2020年度からSDGs動画コンテスト「#SASS(Sustainability Award for Students by Students)」を開催している。
「近年、多くの学校がSDGsをテーマとした探究活動に取り組み始めていますが、その多くは教室内や学校内での成果発表にとどまっています。当法人では、2018年から出張授業などで探究学習を支援しており、生徒たちの活動成果を学校外のもっと多くの方に知ってもらったり、全国の同年代と共有したりしてほしいという想いから、動画コンテストを企画しました」と、同法人の共同代表理事を務める小林真緒子氏は語る。「#SASSに参加することで、探究活動の成果を広く全国に発信するとともに、同世代の生徒同士で刺激を与え合い、切磋琢磨することが可能になります。加えて、動画を通して、探究に取り組む中高生と、運営側の大学生、そして協賛企業をはじめとした産業社会が双方向につながり、社会を変える広がり”を創出できると考えています」(小林氏)。
#SASSへの参加は、1~8名のチームが2~5分の動画作品を応募する形で行われる。応募期間は例年11月から翌2月まで。運営する大学生による一次審査を経て、審査委員による最終審査により各賞が決定し、3月下旬には受賞者が発表される。最優秀賞や作品賞などとは別枠で、協賛・後援する企業・団体がそれぞれ設定したSDGsテーマに基づく特別賞が多数用意されており、SDGsと実社会との接点を見出すきっかけにもなっている。
「最近では、#SASSへの応募をAO入試や総合型選抜に活かして進学する生徒も増えており、探究活動と将来のキャリアをつなげる効果が認められています。今後も、PBLや教材を通じたサポートから、コンテストでの成果発表、さらには卒業後のキャリア支援まで、中高生の探究活動に一貫して伴走することで、将来への可能性や選択肢を広げてあげたいですね」と理事を務める中島幸乃氏は語る。

アンカーの活動の軸となるのが、全国の中学・高校における探究学習支援。各校の先生方と連携してSDGsを切り口としたPBLの企画運営を行い、アンカーのメンバーである大学生がメンターとしてクラスを受け持ち、SDGsの目標達成に向けたアイデアを生徒たちと一緒に考えながら、実践を伴走。さらにはその成果の#SASSでの発表を後押しする。

2018年から継続している探究学習支援の現場で得られた知見やノウハウを活かして、SDGs教育やキャリア教育の教材作成も行っている。例えばワークブックでは、運営側の大学生が作成した課題解決図やライフラインチャート、マイライフシートを多数作成するなど、中高生がSDGsへの取り組み方や、将来のキャリアをイメージしやすいよう工夫されている。
運営する現役大学生と、参加する高校生との交流が、双方に成長をもたらす
本プログラムの最大の特徴は、大学生が主体となって運営していることだ。もともと同法人は、慶應義塾大学院の横田浩一特任教授が、大学の授業とは別に社会課題・地域課題に関心を持つ学生を集めた自主ゼミを母体としている。2018年にゼミ生と共にキャリア教育支援の活動が開始され、活動規模の拡大を踏まえて2021年8月にアンカーとして法人化。現在もゼミ生を中心とした学生やOB・OGによって運営されている。
現役の大学生が運営することで、従来の探究学習にはなかった、より中高生に近い視点でのプログラム提供が可能になっているという。「アンカーに参加する動機やきっかけはそれぞれですが、やはり高校時代に探究活動に熱心だった学生や、教育活動に関心のある学生が多いので、中高生と一緒に考えながら、寄り添うように伴走できるのが強みだと思っています」と小林氏は語る。実際、出張授業後のアンケートでも、年齢の近い大学生の行動力や、挫折を乗り越えた姿に、中高生が大きな刺激を受けた様子が見られるという。
「アンカーに参加する一番のモチベーションは、参加する中高生の成長を目の当たりにできることだけでなく、運営側の大学生も成長の実感が得られること」と小林氏は語る。「中高生を相手に分かりやすく伝えるためには、自身のキャリア観を見つめ直し、言語化する必要があります。その過程自身が貴重なキャリア教育であると同時に、伴走する中高生たちのキャリア観や意識がガラリと変わっていくことに、大きな刺激が得られます。これは大学生にとって得難い経験だと思います」(小林氏)
加えて、運営メンバー同士の交流も成長を後押ししているという。「キャリアや社会活動について意識の高い学生が多いので、自然と刺激を与え合う関係になります。また、PBLの企画や教材作成はもちろん、SNSを通じた情報発信や人脈づくりなど、周囲のメンバーの手法を参考にすることで、将来のキャリアを広げる上で役立つ幅広いノウハウが身に付きます」と中島氏は語る。「学外での課外活動や社会活動に熱心な学生が、あえて自分にない個性や強みを持っていたり、アンカー内にいない興味分野を持った人を連れてくることで、多様な個性や価値観を持ったメンバーが集まっています」という中島氏の言葉から、運営メンバーの多様な個性が、メンバー同士、そして彼らと接する中高生に良い刺激を与えていることが窺える。

大学入学を機にアンカーに参画し、大学院生となった現在も共同代表理事として活動を牽引する小林真緒子氏。「中学時代、何のために勉強しているのか分からなくなり、不登校になった時期がありました。同じ悩みを抱える中高生たちの手助けをしたいと考え、探究学習を通じて将来のキャリアを考えるきっかけを提供しています」と活動に込めた想いを語る。

アンカー理事に加えて、LGBT活動家や学生落語家など、マルチに活動する中島氏。「高校時代にキャリアを学ぶ機会が少ないことに焦りを感じていて、自分でキャリア教育の場を生み出したいと思っていたところ、大学で出会った先輩の紹介でアンカーに参加しました」ときっかけを語る。「アンカーでの活動が、キャリア教育を実践しながら、自らのキャリアを進める絶好の機会になっています」
参加者の広がりと継続的な参画が、活動そのものの持続的な成長につながる
#SASSは2020年度に約600名から144件の応募を受けてスタートし、2023年度には980名、251件まで拡大している。「アンカーが探究学習を支援している中学・高校をはじめとした学校単位での応募が中心ですが、中にはWebサイトやSNSによる口コミなどにより、これまで接点のなかった学校からの応募や、生徒が個人で応募するケースも増えています。学校での探究活動が活性化している中で、#SASSへの応募が探究活動のモチベーションになっているようです」と小林氏は語る。「嬉しいのは、単に応募数が増えるのでなく、参加地域が広がっていること。2023年度は全国29都道府県から応募があり、昨年度から4県増加しています。また、農業高校など実業系の高校からのエントリーも増加しています」(小林氏)。
こうした参加者の広がりを活かすべく、近年では、応募した中高生を対象にオンラインやオフラインのイベントも開催している。「これらイベントでは、運営側の大学生を相手に、あるいは中高生同士で、これまでの人生を振り返りながら、将来どのように社会に貢献したいのか、そのために今、何に取り組むか、などをディスカッションしています。こうした交流を継続することで、互いの悩みを相談したり、活動の仲間を募ったりできるようなコミュニティを築いていきたいですね」(小林氏)。
今後も活動の広がりが期待される一方で、現役大学生が運営主体だけに、活動の継続性が懸念されるが、「そうした不安は全くない」という。例えば、アンカーのメンバーが多数在籍し、SASSの主催団体にも名を連ねる武庫川女子大学では、#SASSの運営に参画することが単位として認定されるなど、大学生が持続可能な形で参画できる体制が整っている。「もちろん大学生なので、学業や研究活動、就職活動などとの兼ね合いで、アンカーを離れるケースもあります。ただ、私たちも含め、メンバー個々が日々、大学生活や課外活動を通じて『面白いな』『一緒にやりたいな』と感じた人を勧誘しているので、マンパワーとしては安定しています。また、最近では、私たちが探究活動をサポートした高校生や、#SASSに参加した高校生が、大学進学後に『運営に加わりたい』と仲間入りしてくるケースも増えており、アンカーの活動を継続してきた成果だと感じています」と小林氏が語るように、運営する学生たちの熱意のバトンが、新たな担い手にしっかりと受け継がれているようだ。
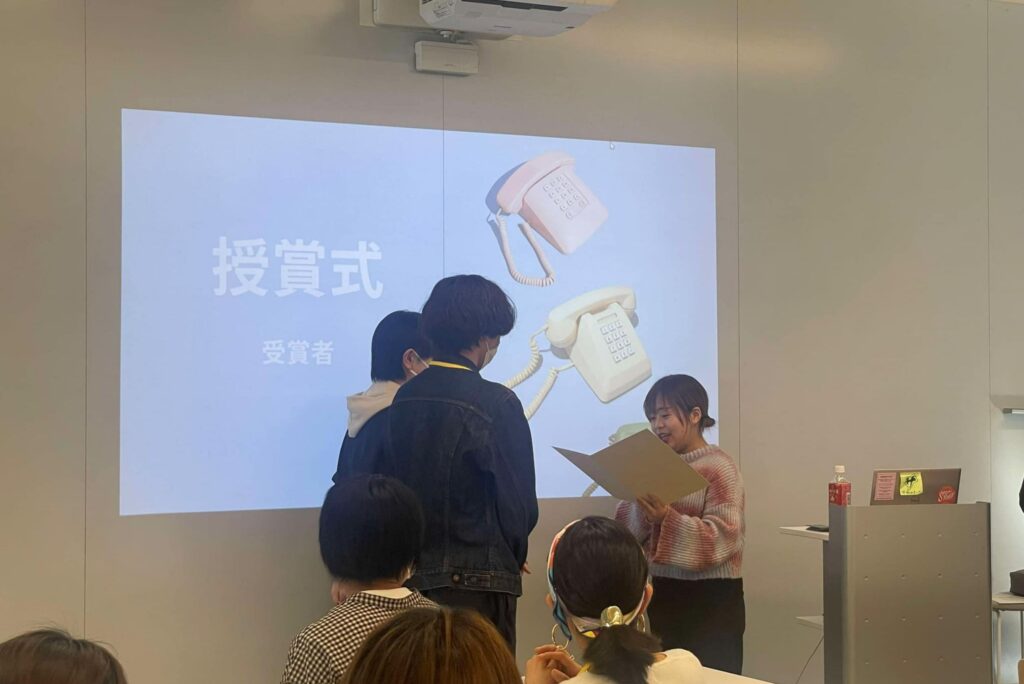
#SASSの審査では、3つの視点から評価される。1つは「考える力-Think-」で、SDGsに基づき社会課題について考え、明確なテーマ設定のもとに探究できているかを問う。2つ目が「行動する力 -Action-」で、調査や問題提起、行動したことなど、個人あるいはグループで計画を立て実行できているかを問う。最後が「伝える力 -Message-」で、映像を通して自分たちの伝えたい社会課題を伝えられているかを問う。

#SASSの審査では、3つの視点から評価される。1つは「考える力-Think-」で、SDGsに基づき社会課題について考え、明確なテーマ設定のもとに探究できているかを問う。2つ目が「行動する力 -Action-」で、調査や問題提起、行動したことなど、個人あるいはグループで計画を立て実行できているかを問う。最後が「伝える力 -Message-」で、映像を通して自分たちの伝えたい社会課題を伝えられているかを問う。

