Program先生による、先生のための、先回り研修プログラム(略称:先3)
~4つのチカラでミライを自作自走する先生コミュニティの創出~
教育改革の後追いにさよならを告げ、未来に先回りして子どもの学びと成長を支えられる先生の育成と先生コミュニティの構築を目指す。具体的には、「探究⇒共創」プロセスの基盤となる批判的思考、創造的思考、論理的思考、対話の4つのチカラにフォーカスを絞り、実社会と学校教育の関係のリチューニングを図りつつ、次世代人材育成の方法論を体系化する。「知ればすぐに動き出したくなる」先生研修プログラムを昭和女子大学現代教育研究所と電通アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所とのコラボレーションによって開発・社会実装し、その普及を図っていきたい。
主なチャレンジは次の通り。
・Hop:4つのチカラを実社会の最前線で活躍されている方々がどのよう場面でどのように活用しているのかを知り、その本質を理解する。
・Step:近未来に必要となる、おもしろくてタメになる学びを自分たちの手で創出できるようになる(⇒日々の授業で「明日から取り組める」知恵を共創)。
・Jump:未来に先回りして、自分たちに必要な学びを自分たちで自作自走できる先生コミュニティの構築を目指す!
【学校法人昭和女子大学-昭和女子大学現代教育研究所】_プログラム紹介(写真・図表)-1024x576.jpg)

活動レポートReport
教育現場の閉塞感を打破して、未来の教育を先回りできる先生を育てていく
「昭和女子大学は、世田谷区にある広大で緑豊かなキャンパスに、附属のこども園から初等部、中高部、大学院までが集約しています。そうした総合学園ならではの豊富なリソースを活かして、教育に関する現代的課題についての調査研究・実践・情報発信を行うことを目的として、2014年に設立されたのが現代教育研究所です」と、2024年度から同研究所の所長を務める緩利 誠(ゆるり まこと)氏は説明する。
同研究所が現在、総力を挙げて展開しているコアプロジェクトが「先生による、先生のための、先回り研修会」、略して「先3(さきさん)」だ。同プロジェクトの背景には、教育改革への対応に追われるあまり、現場の先生たちの元気が失われつつあることへの強い危機感があったという。「近年、社会の要請を受けて、探究的な学びの導入など様々な側面から教育改革が進められています。その方向性自体は納得できるものの、教育現場での本質的な理解を欠いたまま進められているため、『やらされ感』や『疲弊感』につながっているのが問題です」と緩利氏は指摘する。
そこで先3プロジェクトが育成を目指すのが、「ありたい未来を待ち伏せして、教育で先手を打てる先生」、すなわち「先回り先生」だという。「実社会の変化の兆しをいち早く捉えることで、子どもたちが社会に出たときに、どんなチカラが求められるかが理解できます。そのチカラを、先生方が先回りして身に付けながら、子どもたちに身に付けてもらうためのカリキュラムや教育方法、さらには自分たちに必要な研修を自作自走していく。そんな先生方が集まるコミュニティを築いていきたいと考えています」と緩利氏はビジョンを語る。

昭和女子大学の歴史は、大正9年(1920年)に創立された日本女子高等学院に始まる。「世の光となろう」という建学の精神は現代にも受け継がれ、「グローバル教育」「キャリア支援」「プロジェクト活動」などを特徴とした教育が行われている。
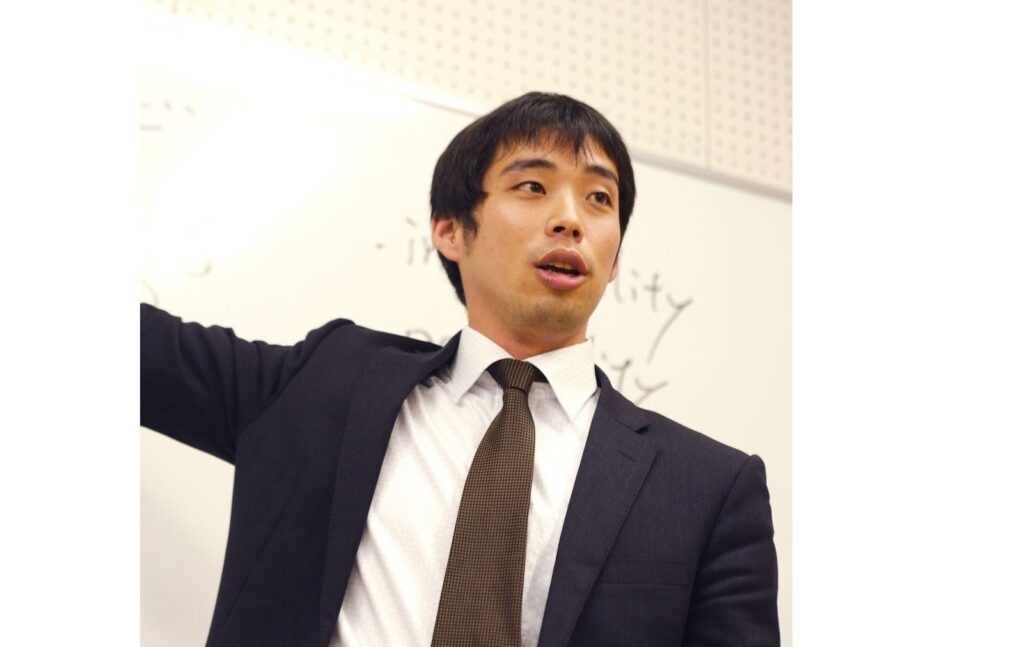
教育学を専門とし、昭和女子大学では准教授として教育課程論や教育方法論を担当する緩利氏。現場の先生方との関わりを重視しながら、学校教育のあり方について積極的に講演・学会発表を行うとともに、著書・論文も豊富。それら経験をもとに「先3」のプロデューサーを務める。
実社会との対話を通じて、これからの教育現場に必要なチカラを培っていく
先3プロジェクトでは、「先回り先生」に必要なチカラとして、「批判的思考」「創造的思考」「論理的思考」「対話」の4つをフォーカス。「いずれも目新しいものではありませんが、私たちが自由に生きるための道具であり、探究学習の成果を実社会での課題発見・解決に活かしていくための基盤となるものと捉えています。大切なのは、これら4つのチカラが実社会でどのように活用されているかを理解し、自ら実践できるようにすること。そこで本プロジェクトでは、実社会の動きを批判的に吟味しながら、近未来に必要とされる学びを論理的に導き、そのための具体的な実践を自ら創造していくことを目的としています」と緩利氏は語る。
実社会と結ぶキーとなるのが、プロジェクトの運営パートナーである電通「アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所」が持つ異業種の視点とクリエイティブな発想、幅広いネットワークだ。「初めて同研究所と連携した際に、教育界に閉じた議論に終わらず、実社会の課題との共通点を見いだしながらクリエイティブな解決策を探ろうとする姿勢に、常識を揺さぶられる想いがしました。その時のワクワクした気持ちを現場の先生方にもぜひ感じてほしいと考えました」と緩利氏は振り返る。
両研究所のタッグのもと、先3プロジェクトでは異業種から招いた講師陣との「対話」をベースに、4つのチカラの本質について改めて考えてもらう研修を企画。2022年12月には「先生のためのロジカルシンキング」、23年2月には「先回りして考えてみる『答えのない問い』」をテーマとしたトライアルを実施。いずれも約80名の参加者を集め、8割以上から「明日からのヒントを得ることができた」との評価が得られた。

「先生方の学びにもワクワク感が必要」との観点から、知識伝達型の研修ではなく、知ればすぐに動き出したくなる対話型、共創型の研修となることを目指した先3プロジェクト。2022年度のトライアルを通じて、動画も含めた多様な講師陣による先回りレクチャーと、参加者が自分事化するための問いに対するディスカッションを組み合わせた研修スタイルが確立された。

電通「アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所」は、2015年の設立以来、さまざまな教育コンテンツを提供。先3プロジェクトでは、同研究所の発想や人脈、リソースを活かして、グラフィックデザイナーやゲームクリエイター、建築家、スポーツ選手、ミュージシャンなど幅広い講師陣が招かれている。
「先回り先生」たちのコミュニティを全国、そして世界に広げていく
2022年度の試行実施を経て、初年度となる2023年度は10月から月1回のペースで全6回のプログラムを開催。前半4回で4つのチカラを培った上で、後半2回では参加者それぞれが磨き上げてきた教育の技を発表し合いながら、新たな一歩を踏み出すための企画会議を行った。主に高校の先生と、将来高校教師を目指す学生を対象とし、WebサイトやSNS、全国の先生方へのネットワークを通じて告知した結果、全回通しチケットは完売となり、毎回、ほぼ定員が埋まるほどの反響を得た。「オンライン参加も可能なハイブリッド開催としたことで、北海道から九州まで全国から参加いただけました。加えて、ベテランから若手、学生まで幅広い層がバランス良く集まったことで、いろいろな視点からの議論ができたことは収穫でした」と緩利氏は手応えを語る。
参加者の満足度も高く、「自分の内なるところから出てくるものが重要だと感じた」「先回りとは、ただ他人より新しいことをやるのでなく、未来へのビジョンを持ちながら取り組むことだと気づいた」といった声が聞かれたという。緩利氏が特に印象的なのが「1%の側が99%を巻き込まなければという覚悟ができた」という言葉であり、「参加者それぞれが自身の学校で周囲を巻き込んでいき、教育界全体に“うねり”を起こすことを期待していますし、私たちもそんな先生方を支え続けていきたい」と抱負を語る。
もう1つの狙いが「全国各地の先回り先生たちが、お互いに触発しあって先回りする教育を自作自走していけるコミュニティにしていくこと」だという。「メインの研修プログラムに加えて、オフ会も開催するなど、参加者同士のコミュニケーションの場を充実させるとともに、実行委員会への参画やスピンオフ企画の運営、所属する学校での講演会・勉強会などの開催も呼び掛けるなど、その場限りの取り組みで終わらせないよう工夫しています」(緩利氏)。
参加者からの意見や要望も反映しながら、2024年度以降も継続的な開催を予定しているが、将来的な目標とするのはフィンランドの非営利教育団体HundrEDのような世界的な存在になることだという。同団体は革新的で拡張性のある教育アプローチを世界中に伝えることをミッションとしており、毎年発表するレポートは世界の教育界から注目されている。「日本の教育レベルは非常に高いものがありますが、世界への発信力があまりにも弱い。私たちが国内におけるHundrEDのような存在となることで、世界的な動きを日本に取り入れると同時に、日本の教育の良いところを活かして世界的な教育のレベルアップに貢献していきたい」と緩利氏はビジョンを語る。
先3プロジェクトで育まれた先回り先生が、それぞれの学校を元気にし、その輪が広がることで、やがては日本中、ひいては世界中の教育現場をよりクリエイティブでワクワクしたものにしていく。そんな未来に期待したい。

セッションやオフ会での参加者同士の対話風景。校内研修、行政研修に続くサードプレイスとして、先回り先生たちのコミュニティとなることを目標とする先3プロジェクト。毎回のセッションやオフ会などを通じて、参加者同士の対話も深まり、プログラム修了後も交流が継続しているという。

2024年度のコンセプトは「守破離」の「破」。既存の枠やルールなどを破ることで、新たな教育の創造を目指す。9月から月1回で「ゆるめる」「減らす」「発想する」「軸を作る」「調べる」「先回る」という6回構成を予定しており、前回からの継続参加も含めて、すでに多くの参加希望者が集まっている。詳細は https://saki3.swu.ac.jp/

